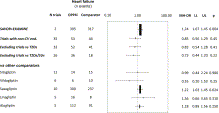ロドデノール配合の化粧品を使用して肌がまだらに白くなったという事例が報告され、2013年カネボウ化粧品とその関連会社は、化粧品と白斑との関連性が懸念されるとしてこの成分を配合する8ブランド54製品を自主回収しました。この有害事象は現状十分に解明がされていない状況でありましたが、ロドデノールの毒性に関する詳細な基礎研究が報告されていましたので一部主要部分をご紹介いたします。なお訳には自信がありませんので、詳細は原著論文をご確認ください。
Sasaki
M1, Kondo M, Sato K et al Rhododendrol, a depigmentation-inducing phenolic compound,
exerts melanocyte cytotoxicity via a tyrosinase-dependent mechanism. Pigment
Cell Melanoma Res. 2014 May 29. PMID: 24890809
[はじめに]
Rhododendrol
(4-(4-hydroxyphenyl)-2-butanol, Rhododenol®)ロドデノールは白樺など天然に存在するフェノール化合物で、化粧品として肌の美白を目的に研究開発がなされてきました。その後、ロドデノール2% (w/w)を含有する製品が市販化され、本邦では約5年にわたり、入手が可能でした。しかしながらロドデノールがdepigmentary disorder(ロドデノール誘発性白斑)を引き起こしている可能性を示唆する報告が相次ぎ市場から消えました。
有害事象 発表後約6ヶ月の時点では、色素脱色の症状はロドデノールを含む化粧品の推定使用者800000人のうち約 16000(2%)で確認されていました。症状は、主に薬品と繰り返し接触した部位で観察され、6ヶ月間使用を中止していた被害者の79%は改善傾向を示しました。臨床的および病理学的詳細はまだほとんど知られていない、このロドデノール誘発性白斑の病因は、緊急の明確化が必要でした。
化学物質による白斑は、表皮メラニン細胞に損傷を与える特定の物質への反復暴露によって引き起こされた色素の脱色と言われています。原因となる化学物質は、フェノール、カテコール類など大部分は芳香族または脂肪族誘導体ですが、例えば、スルフヒドリル、水銀、ヒ素、桂皮アルデヒド、p-フェニレンジアミン、ベンジルアルコール、アゼライン酸、コルチコステロイド、エセリン、チオテパ、クロロキン、およびフルフェナジンなども同様に脱色効果を引き起こすことが可能であると言われています。ただ致命的であることを示唆する根拠はありません。
ヒドロキノンのモノベンジルエーテル(MBEH)及び4-tert-ブチルジフェノール(4-TBP)は特発性白斑を引き起こすことが知られているフェノール系化合物として広く知られていました。MBEHにさらされた患者は、一般的に永久的な脱失を受けると言われています。また、4-TBP化合物は、ゴム、皮革業界で働く個人に職業白斑の原因となり、特にメラニン細胞に対して細胞毒性であることが示唆されています。これらのフェノール化合物の作用メカニズムは不明確な部分が多いもの、化合物の特徴としてチロシンにたいして構造的類似性を持つことからメラニン生成の律速酵素であるチロシナーゼに対する基質として作用することが考えられています。メラニン細胞チロシナーゼの触媒作用により、フェノール化合物からの反応性のo-キノンラジカルの生成をもたらし、これが酸化的ストレスや細胞毒性を誘導する可能性が考えられています。具体的には4-TBPは、アポトーシスを引き起こし、一方、MBEHは、非アポトーシス細胞死(壊死性の細胞死)を誘導すると言われています。
本研究では、フェノール化合物との繰り返しの接触によって引き起こされた可能性のあるロドデノール誘発性白斑のメカニズムを理解するために、培養ヒトメラノ細胞に対するロドデノールの影響を調べた
[結果]
▶ロドデノールは培養ヒトメラニン細胞のチロシナーゼ活性を抑制する。
▶ロドデノールはマッシュルームチロシナーゼに対し、競合阻害を引き起こす
ヒトメラニン細胞におけるチロシナーゼ活性を抑制効果とともに、マウスメラノーマ細胞におけるメラニン生成の抑制が確認されています。ラインウィーバー·バークプロット分析1)より阻害様式は競合阻害を示しており、チロシナーゼの基質として作用している可能性があります。
▶ロドデノールはマッシュルームチロシナーゼのための良好な基質として働く
▶チロシナーゼ活性はロドデノール細胞毒性のために必須である
▶ロドデノールは、ヒトメラニン細胞において検出可能な活性酸素種(ROS)を誘導しなかった
(ロドデノール⇒(チロシナーゼ)⇒代謝産物の細胞毒性)
L-チロシンのKmに匹敵値するほどの反応速度で基質として働く可能性が示唆されました。ロドデノールはメラニン細胞内のチロシナーゼ活性によってキノンロドデノールに酸化されることを示唆しています。ロドデノールはチロシナーゼ活性を阻害し、メラニン形成を阻害しますが、阻害様式は競合阻害のため、自身が酸化され、そのキノンロドデノールが細胞障害を引き起こす可能性が見いだされ、同時にロドデノール細胞毒性作用はチロシナーゼ活性に依存していると言えます。一方で、活性酸素の有意な検出はできませんでした。
▶ロドデノールはチロシナーゼ依存的に小胞体ストレス応答を活性化させる
▶ロドデノールはカスパーゼ3を活性化するが、チロシナーゼsiRNAによりその活性化が阻害される
ロドデノールは、ヒトメラニン細胞におけるカスパーゼ-3の活性化2)を誘導し、チロシナーゼsiRNA3)は、その活性化を阻害することからロドデシノールに誘導されるカスパーゼ3活性化はチロシナーゼに依存していることが示唆された。
[結論]
以上より、ロドデノールのメラニン細胞毒性は活性酸素などによる細胞障害の可能性は低く、チロシナーゼによる酸化をうけたロドデノール代謝物が小胞体ストレス応答の活性化、あるいはカスパーゼ3を活性化、もしくはその両方の経路でアポトーシスを誘導することにより、細胞毒性を発現する可能性が示唆された。
[訳者注釈]
1)酵素の阻害証式はラインウィーバー•バークプロットという手法を用いることで判別できる。競合阻害様式は、本来のチロシナーゼの基質であるチロシンにロドデノールが構造的に類似しているため、チロシナーゼ反応物の生成が阻害される様式である。ロドデノールもチロシナーゼと良好に反応することがミカエリス定数(KM値)より推測され、容易にロドデノール代謝物が生成される。本事例における細胞毒性はこの代謝物によるものと考えられている。
2)カスパーゼや小胞体ストレス応答はいずれもアポトーシスに関わる重要な経路。
3)siRNAとはRNA干渉することで配列特異的にタンパク発現を阻止する小さなRNA。実験的にはsiRNAを細胞内へ注入し、配列特異的にタンパク合成を抑制することができる。チロシナーゼを発現するための遺伝配列に対するsiRNAを投与することにより、チロシナーゼの発現を抑制することが実験的に可能となります。チロシナーゼ抑制でアポトーシス誘導経路の一つであるカスパーゼ活性化が阻害されたことから、ロドデノールのアポトーシス誘導にはチロシナーゼが関わっており、かつ細胞障害機構はネクローシスではなくアポトーシスである可能性が示唆されています。